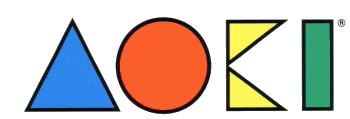月例坐禅会
慈眼院の月例坐禅会へ行く
9月14日、月例の坐禅会へ参加する。きょうは5名の参加者だ。初めて参加される方がいるので、坐禅法を説明する。台風18号が接近している。その影響で南東風となっているから、とても蒸し暑い。3炷終わって、ほっとする。 書院には …
慈眼院の沙羅双樹
南寿明和尚様から、嬉しいメールが届いた。慈眼院の庭にある、沙羅双樹の花が咲いたとのことだ。今年は念願を叶えたい。
6月1日の月例坐禅会
開始時刻が迫っていたが、手洗いに行ってから道場へ入る。始めての参加者がおられたので、坐禅のやり方を一渡り説明する。日が長いので、道場内はまだ薄明るい。 いつの間にか三炷が終わる。本堂から書院へ渡る廊下の下は、鎌倉時代の遺 …
4月27日の月例坐禅会
穏やかな夕方だ。慈眼院の駐車場には、白と薄紫の芝桜が咲いている。 障子を開けて本堂へ入ると、もうすでに香が焚かれている。2回欠席したので、久しぶりだ。今日は初めての方が2名参加された。参加者の5名が3炷の坐禅を終えた。2 …
凍り付く中での月例坐禅会
こんなに寒い日には、誰も参加者はいないに違いない。しかし慈眼院には、すでに参加者が待っておられた。私も入れて、5人だ。 本堂には座布団が並べられている。先に着いた人が、並べてくれたのだろう。靴下を脱いで、座布団に坐る。寒 …
12月8日の月例坐禅会
きのうは、嵐だった。大阪湾では西風が15m以上吹いている。海上は白波だらけだ。時折あられまで降ってくる。練習に出ていったヨットも、すぐに帰ってきた。 仕事を終えてから慈眼院へ行く。入り口を開け放して堂内へ入る。この寒さで …