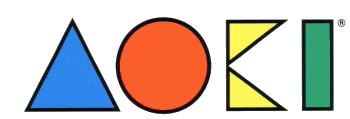アジア内海
ベトナムの古い港町ホイアンへ・1
お正月休みを利用して、ベトナム中部の古い港町であるホイアンを訪ねた。旧市街が世界遺産に登録されて以来続きを読む…
沖縄県立博物館から戻る
7月9日から12日にかけて、沖縄県立博物館・美術館と浦添市美術館へ調査に行く。沖縄の船舶古絵図を調査続きを読む…
日本の海岸線長さは世界6位
日本の国土面積の広さは、世界で62位であるが、海岸線長さは6位である。国土面積が少なく、そしてさらに続きを読む…
沖縄の県立博物館を訪問
関空からマイレージを利用して、那覇へ行く。那覇からはレンタカーで糸満へ直行する。青木ヨットから購入頂続きを読む…
航海者から見た、アジア内海の船と航海術・・・目次
航海者から見た、アジア内海の船と航海術・・・Preview 1. 航海者からアジア内海を位置づける 続きを読む…
航海者から見たアジア内海の舟と航海術
1-2 アジア大陸に沿った帯状のアジア内海 前回に示した大陸側から見た地図を眺めると、アジア大陸に沿続きを読む…
航海者から見たアジア内海の歴史と文化
1-1 大陸側から見た日本列島弧の位置 島嶼問題を巡り、国家間の関係がぎくしゃくしている。日本列島弧続きを読む…