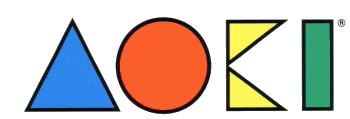ヨット
ベトナムの古い港町ホイアンへ・1
お正月休みを利用して、ベトナム中部の古い港町であるホイアンを訪ねた。旧市街が世界遺産に登録されて以来続きを読む…
亀岡の、みずのき美術館を訪問した。
楽々荘で待ち受けていたのは、とんでもなく面白い人との出会いだったが、その話はまたの機会にしよう。 旅続きを読む…
「旧暦と暮らす」を読む
「旧暦と暮らす」はヨットで世界一周した建築家、松村賢治さんの著書だ。松村さんは南太平洋教会の理事長で続きを読む…
沖縄の県立博物館を訪問
関空からマイレージを利用して、那覇へ行く。那覇からはレンタカーで糸満へ直行する。青木ヨットから購入頂続きを読む…
1/13 青木ヨットスクール:横須賀プラクティスコース 開催
・ASA青木ヨットスクールのトレーニングシステムがすばらしい。 ・インストラクターからの励ましの言葉に勇気付けられました。
きのくに子どもの村学園のヨット作り-1
11月27日は会社の定休日だ。自動車で和歌山県橋本市の山中にある、きのくに子どもの村学園を訪れた。橋続きを読む …