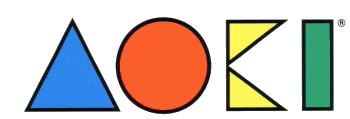坐禅
8月9日の月例坐禅会は台風接近のため中止
来月の慈眼院坐禅会は9月6日(土)の午後6時30分からです。
7月の月例坐禅会に参加
7月26日に泉佐野市の山手にある古刹、慈眼院での月例坐禅会に参加した。猛暑日だったので来る人は少ない続きを読む…
月例坐禅会へ参加する
5月10日の、慈眼院で行われた坐禅会に参加した。今月は6名の参加者だ。 今年もまた花の季節が巡ってき続きを読む…
3月1日の月例坐禅会に参加
市民坐禅会の会場として毎月使わせて頂いているのは、泉佐野市の山際にある慈眼院だ。慈眼院は673年に、続きを読む…
1月25日の月例坐禅会に参加する
今日は6名の参加者だ。温暖前線が接近しているためか、暖かい。本堂の中よりは、外の方がむしろ暖かく感じ続きを読む…
12月8日の月例坐禅会
きのうは、嵐だった。大阪湾では西風が15m以上吹いている。海上は白波だらけだ。時折あられまで降ってくる。練習に出ていったヨットも、すぐに帰ってきた。 仕事を終えてから慈眼院へ行く。入り口を開け放して堂内へ入る。この寒さで …
11月3日の月例坐禅会
18時に会社を出て、慈眼院へ向かう。駐車場へ車を止め、門前で一礼する。本堂へ入ると、すでに6名の方が来ておられた。坐禅は初めてという2名の方に、坐禅法を説明する。 肌寒い夜だが、瞑想はとても深まる。いつの間にか2時間が過 …