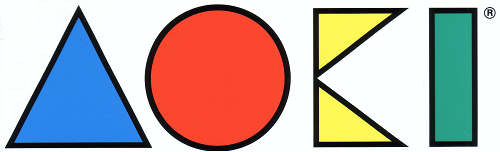装備
夜間の機帆走について
Q:夜間に機帆走する場合は、前照灯、船尾灯、両舷灯を点灯しますが、この場合ジ ブを使うと、ジブの展開続きを読む
ボートトレーラー新規登録及び車検手順
ディンギー及び、小型ボート、ジェットスキーを車でけん引する際に、必要となってくるのがボートトレーラー続きを読む
ブームキッカー、トッピングリフトの長所・短所について
Q:ブームキッカーの難点は何ですか。 ワイヤー製のトッピングリフトが現在多くの船で使われているので、続きを読む
オートパイロット取り付け作業 54,000~(税・商品代別)
オートパイロットは長距離航海が飛躍的に楽になる、非常に便利な装備です。 本体を舵にセットし方位を入力続きを読む
GPS魚探取り付け作業 50,400円~(税・商品代別)
近年の船用GPS魚探は性能も向上し、カーナビに引けを取らない機能で航海をサポートしてくれます。 より続きを読む
検査および登録の対象にならない帆船
Q:小型船舶の学科教本によると、法的に は「長さ12メートル未満、沿海区域を越えて航行しない帆船は検続きを読む
ヨット用のライフジャケット
Q:ヨット用のライフジャケットは何種類もあるようですが、どのような種類を選べばよいでしょうか。 A:続きを読む
子供用のライフジャケット
Q:子供用のライフジャケットを選ぶときは、どのような製品がよいでしょうか。 A:12歳以下の場合は、続きを読む
ボート用のライフジャケット
Q:ボート用のライフジャケットは何種類もあるようですが、どのような種類を選べばよいでしょうか。 A:続きを読む
ライフジャケットを着けるのはどんな時
Q:穏やかなときでもライフジャケットを着けなければなりませんか。嵐の時だけでよいのでは? A:ライフ続きを読む